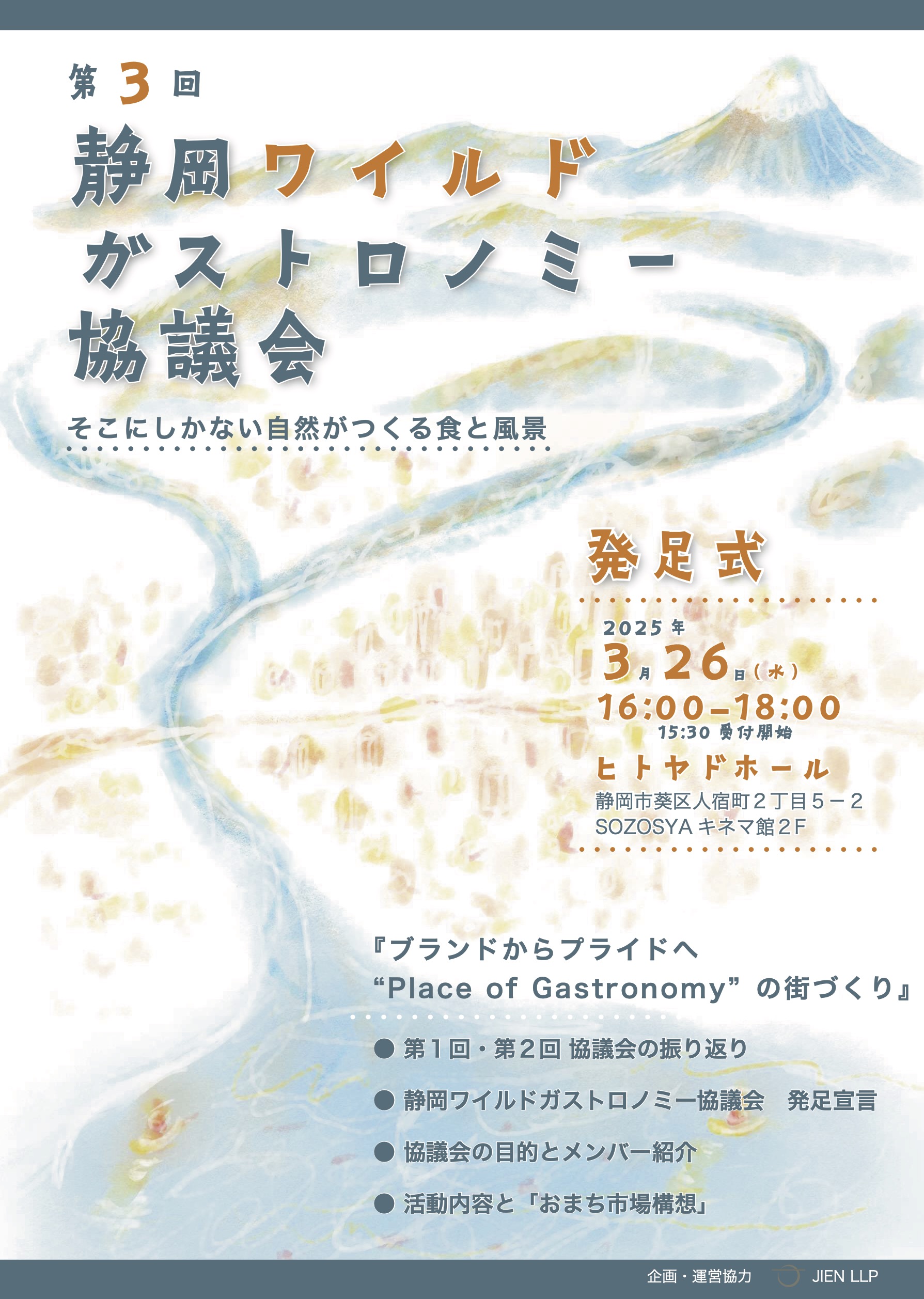静岡新聞の橋爪教育文化部長が7月20日(土)の南アルプスユネスコエコパーク登録10周年記念連続シンポジウム 第3回「南アルプス高山植物由来酵母とウイスキー&交流会」ご来場頂き、番組内の静岡トピックスで取り上げて下さいました。
南アルプスの高山植物から分離した酵母による静岡のウイスキーの話のなかで二つのキープレーヤー機関があります。
一つは南アルプスの井川蒸留所で、標高1200mの日本一高いところにある醸造所で、木賊湧水の水を使ってウイスキーを作っています。椹島ロッジのさらに奥にあり、車で4時間20分かかったそう。ジャパニーズウイスキーは3年熟成させなければならず、この秋からいよいよクリアしたウイスキーが世に出ます。
もう一つは静岡大学学部横断産官学連携文理融合組織である発酵とサステナブルな地域社会研究所(通称「発酵研」)で、静大各学部のジャンルを横断し串刺しにした研究組織で、中世ヨーロッパのビールを再現したいところから始まり、去年の家康公クラフトの発売に至っています。徳川家康ゆかりの場所から花酵母を採取してオリジナルビールを作るプロジェクトは市の観光振興と大河ドラマ『どうする家康』とタイミングが合い、静岡市内のアオイブリューイング、Horsehead labs、静岡醸造の3つの醸造所から三種類作られました。すぐに売り切れてしまいなかなか飲めないビールとして記憶されています。
この二社がコラボして発酵研で採取した南アルプス高山植物由来酵母でウイスキーをつくるプロジェクトが進んでいます。麦芽を糖化させて発酵させるビールと途中まで作り方が同じモルトウイスキーを南アルプスの酵母も使ってつくるというものです。
SBSラジオの読み上げニュースでも告知して頂いた「南アルプス高山植物由来酵母とウイスキー&交流会」では興味深い話がいくつもあり、なかでも沼津工業技術支援センターバイオ科の鈴木主任研究員がヤマザクラやモクレン、シャクナゲなどから分離した酵母にどれだけ力があるかを分析した話がおもしろかったそうです。サッカロマイセス・セレビシエのなかからアルコールを作り出す力が強い4種類と市販のエール酵母、ウイスキー酵母を分析し、野生酵母4種類中4種類がアルコール発酵能が高く、ウイスキー醸造のポテンシャルがあると結論付けられています。
ハクモクレンの酵母のウイスキーは口に含むと野生の草木のかおりが口に広がり、水を加えると荒々しさが甘くなりけれども芯の部分は崩れない骨格の強さを感じたそうです。このニューボーンは2027年にウイスキーになります。南アルプスの酵母で醸したウイスキーが南アルプスで眠っているのは夢があり、クラフトビール王国、吟醸王国、そこにもってウイスキーの面白い展開が期待できます。
最後に南アルプスユネスコエコパーク登録10周年記念連続シンポジウム 第4回 「南アルプスの水と酒造り」についても告知して頂きました。
10月13日(日)14時00分~16時20分にレイアップ御幸町ビル 5-D会議室にて開催されます。今度は日本酒の話で女泣かせで有名な大村屋酒造場の日比野さんは静岡大学大学院農学研究科出身の異色の経歴を持つ杜氏さんが「南アルプスの水と酒造り」についてお話くださいます。7月講演会で発表された鈴木さんが清酒造り、静岡県オリジナル種麹について、また人文社会科学部の貴田先生が「室町時代における酒造業と社会」と歴史について講じて頂くという理系的話と文系的話が混在するシンポジウムです。
このようなシンポジウムを通して知って飲む、そして蘊蓄があればあるほどそれぞれのお酒に対する愛着、作り手への尊敬、そしてストーリーや歴史、作られている場所のバックボーンを知れば知るほど県外の人に教えたくなる、酒は文化遺産であるとしていました。